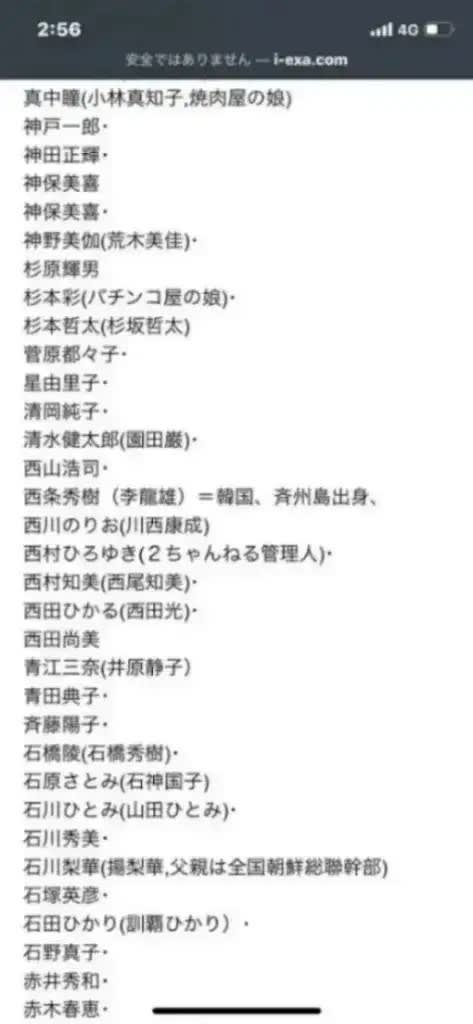第155回芥川龍之介賞受賞作で、とても話題になり好セールスを記録した本だが、私もやっと読んでみた。なるほど、かなり面白い。主人公の造型がユニークであるばかりではなく、そのキャラクター設定の“切り口”が卓越している。また個人と社会との関係性、および両者の間に介在する“越えられない壁”の描出に非凡なものを感じる。読後感は良い。
主人公の古倉恵子は、36歳の独身女性。結婚したことはなく、恋愛経験すら無い。子供の頃から感情に乏しく、他の人間と上手くコミュニケーションが取れなかった。そんな彼女が大学時代に始めたコンビニのアルバイトが意外にツボにハマり、正社員にならないままバイトの身分で今まで生きてきた。しかし、いい年をして独り者の恵子に対する周囲からのプレッシャーは次第にキツくなる。
そんな時、彼女はかつての元バイト仲間で、人間のクズみたいな白羽という男と再会する。恋愛感情も無いまま成り行きで彼と同居することになった恵子だが、すると彼女に対する“評価”が一変。一応男と付き合うようになったのだという事実が、彼女が“まともな人間”であったとの周りの認識に繋がり、恵子も満更ではないと感じる。やがて、恵子がコンビニを辞める日がやってきた。
恵子はモノの考え方が常人とは異なっている、生まれながらのサイコパスである。ところが、彼女がコンビニという極端にシステマティックな媒体と出会うことにより、そこに“同化”してしまう。その着眼点には驚くしかない。
対する白羽は典型的なロクデナシの落伍者だ。社会の異分子であることは間違いないが、こういうキャラクターは珍しくはない。いわば白羽は旧来型のサイコパスで、恵子はニュータイプのサイコパスだ。もちろん恵子のような性質を持つ者は以前から存在したのかもしれないが、小説として正面から取り上げたことは実に新鮮に見える。
また、本作は個人と“世間”との隔絶を大きくクローズアップさせる。先天的に他人と異なる“属性”を備えた主人公を、周囲の者はしきりに“治そう”とするのだから滑稽だ。しかも、ちょっと異性と付き合っただけで(本人の内面は変わらないのに)“治った”と合点してしまう。ラストシーンはある意味痛快で、ハッピーエンドとも思えるのだが、本人以外にとってはバッドエンドであるのも面白い。
関係ないが、恵子のような者は実は社会的に有用だということも言える。彼女は情緒に流されず、いかなる忖度も通用しない。目標を見定めると冷徹かつ合理的に事を進めるだけだ。成功者にはサイコパスが多いという説があるのも、まあ頷ける。